漆塗り工程(座卓、布目朱溜塗り)
漆塗りの工程は、大まかに下地付けの工程と、ハケで漆を塗る漆塗りの工程に分けられます。
下地付けも、漆塗りも十分な日にちをおいて、よく乾かして、しまりをよくしてから、次の工程に移らなくてはなりません。これを、よく”涸らす”といいます。
そして、漆塗りは、下地を何回も付けては砥ぎ、漆を塗っては研ぐ、という気が遠くなるほどの手間と時間がかかります。
俗に、”塗師やの3年”といわれる程、大変長い日数がかかります。
手間と、漆の材料と、涸らす長い日数ゆえに、漆器や漆塗り家具は、費用がかかり、どうしても高級な物になります。
座卓の漆塗りを例にとり、工程の一端を紹介してみたいと思います。
下地付けも、漆塗りも十分な日にちをおいて、よく乾かして、しまりをよくしてから、次の工程に移らなくてはなりません。これを、よく”涸らす”といいます。
そして、漆塗りは、下地を何回も付けては砥ぎ、漆を塗っては研ぐ、という気が遠くなるほどの手間と時間がかかります。
俗に、”塗師やの3年”といわれる程、大変長い日数がかかります。
手間と、漆の材料と、涸らす長い日数ゆえに、漆器や漆塗り家具は、費用がかかり、どうしても高級な物になります。
座卓の漆塗りを例にとり、工程の一端を紹介してみたいと思います。
漆下地の工程
下地は、漆の下地以外にも、渋下地や、にかわの下地などがありますが、漆の下地がやはり、一番強いです。ここでは、漆の下地の工程を紹介してみたいと思います。
木地の表面を研いで整えます(木地調整)

この座卓は、古い座卓です、表面をきっちりペーパーや砥石で研いで、木地調整をします。
新しい木地でも同様です。これは、木地を整えるという意味の他に、漆をよく染み込ませて、密着させるという意味で大変重要です。
生漆を染み込ませて木地を固めます(木地固め)

糊漆で布を貼り付けます(布貼り)
米糊と、生漆を混ぜて、糊漆を作り布を貼ります。






1回目漆下地付け(切粉地付け)
地の粉とトノコを水で練り、さらに生漆と混ぜ合わせて、下地を作り(切粉地)、ヘラで布の目にしごき入れるように、下地をつけます。




下地砥ぎ
つけた下地をよく涸らしてから、荒砥石でざっと研いで、下地の表面を滑らかにします。
2回目漆下地付け(漆錆付け)
トノコと水を練り、さらに生漆と混ぜて、下地を作ります。これを”漆錆”と呼びます。これをヘラで薄く付けます。






下地仕上げ砥ぎ
目の細かい砥石で、丁寧に水砥ぎします。




下地に生漆を染み込ませて、下地を固めます(下地固め)


漆塗り工程 (漆朱塗り、溜塗り)
今回は、中塗りには、朱漆を塗って、朱塗りにしました。
上塗りは、中塗りの朱塗りの上に、透き漆を塗って、溜塗りとし、朱溜塗りの仕上げにしました。
朱塗りと、溜塗りの違いが分かるかと思います。
上塗りは、中塗りの朱塗りの上に、透き漆を塗って、溜塗りとし、朱溜塗りの仕上げにしました。
朱塗りと、溜塗りの違いが分かるかと思います。
漆と朱の顔料をよく練りあわせて、濾し紙で濾します (漆、朱練上げ)
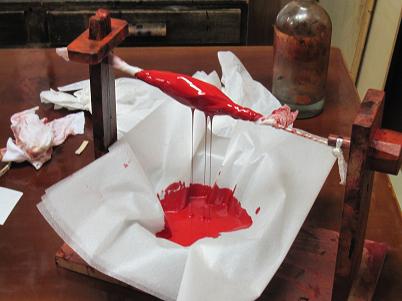
朱漆を塗ります(朱塗り、中塗り)



布目朱塗り(中塗りが乾きました)

駿河炭で朱塗り(中塗り)の表面を水砥ぎします(中塗り砥ぎ)


上塗り用の透き漆を何回も濾し紙で濾します(漆濾し)

透き漆で上塗りをします(溜塗り)

布目朱溜塗りの座卓が仕上がりました (艶消し仕上げ)
ご 案 内
会社名 大東漆木工(おおひがしうるしもっこう)
〒602-8491 京都市上京区西社町198−1
TEL 075−432−0043
〒602-8491 京都市上京区西社町198−1
TEL 075−432−0043
和家具製作と漆塗り、京都の大東漆木工





